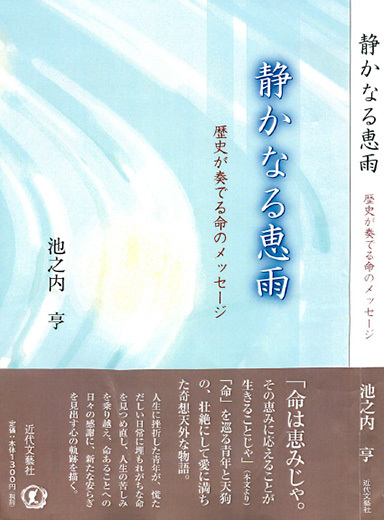【死】死に向き合う真の意味とは何か?

表題のテーマは、本講座第一回に通じてまいりますが、講座全体を通じて重要なテーマになっている重要なものです。長文とはなりますが、お付き合いいただけましたら幸いです。
さて、死に対して、いいイメージを持っている方はおられないと思います。
「死は恐ろしい...」
「死を克服できる者など誰もいない...」
「死のことを考えても何もいいことなどない...」
それが普通の考え方でしょう。
だから、これだけ情報がオープンになった現代社会でも、死のことはタブー視されます。
でも、本当は違います。
その証拠に、哲学の分野では「人生とは死について学ぶこと」とされるほど、死について学ぶことが重要視されます。実際、哲学三千年の歴史において“死”は最大のテーマであり続けています。人類の未来が不透明で、生きづらい社会にいる現代では、ますます死について学ぶことが必要とされている気がします。
以下、死について学ぶメリットについて、ポイントのみをお話します。
==目次==
1.世界の本質は“愛”
2.“愛”による救済と喜び
3.”愛”に立脚した新しい生き方
4.死を知る本当の意味
1.世界の本質は“愛”
さて、死を深く洞察しようとすれば、“存在”とは何かについて究明しなければなりません。
この領域は最先端科学の得意とするところです。詳細は省かせていただきますが、それにより、世界の真の姿が明らかになりつつあります。
その姿は誰もが驚き、ため息を漏らすほど、私たちの日常的認識とは全くかけ離れています。相対性理論のように、常識的な時間や空間の概念があてはまらないばかりではありません。それどころか、物質の概念、さらには実在の概念でさえ従来の概念があてはまりません。
その理論は量子論と呼ばれますが、あまりにも私たちの常識と相いれないため、量子論が誕生した1900年以降、何と100年以上も実証実験が繰り返されてきました。そして、ようやく、最先端技術を駆使して、その正しさが実証され、2022年にノーベル物理学賞が与えられたという次第です。
少し余談になりますが、量子論は産業革命を牽引したニュートン力学的世界観を根底から覆しました。世界が物質から構成され、確定した未来に向かって進んでいるという馴染み深い描像が根本的に誤りであり、世界の本質は決定論的ではないことを示したのです。このアイデアは私たちの自由意志や将来を創造する励みの意味に大きな影響を及ぼしています。私たちは今後、量子論に基づく世界観、そして、価値観を創造していくことを求められることになります。
さて、戻ります。
量子論から描かれる世界観の本質は、一言でいえば、世界が一体であること、つまり、世界のどの部分も切り離しては考えられないということです。そして、そこには私たちを魅了してやまない人知を超えた調和が内包されています。もし、ここで仮に、世界が垣間見せる素晴らしい調和の構造の本質が“愛”であるといわれれば、あなたはどう思いますか?
科学的世界観のいきつく先が、非科学的な“愛”?と驚くかもしれません。でも、ここでいう“愛”とは私たちのイメージするものとは少し異なり、稀代の天才科学者アインシュタイン博士が娘リーゼルへ送った手紙に記された愛と捉えてください。
彼は、宇宙の本質的力が愛であると述べた時、世界中から誤解されることを予感していました。それを「私が相対性理論を発表したとき、世界の誰にも理解されなかった。今回のことについても同様であろう。だから、この手紙は世界がそれを理解できるようになるまで何年でも何十年でも守ってほしい」と書き残しています。
また、彼は、“愛”を数式では表わせないものの科学的な力として捉え、宇宙を支配する極めて根本的な力だと考えました。現代の言葉でいえば、存在するものの間にはたらく“調和としての相関”という意味に解釈してよいかもしれません。
それが世界の原理であるとするなら、世界の本質は“破壊と消滅”ではなく、秩序や調和を創造する“受容と和解”ということになります。そうであれば、私たちの世界観や人生観はまったく違ったものになるでしょう。生の無意味や人生の絶望には、きっと希望の灯がもたらされるに違いありません。
ところで、アインシュタイン博士は科学史に数々の偉大な業績を残すほど科学的精神の持ち主だったにもかかわらず、“神”の存在を信じていたとされます。しかしながら、それは宗教的な神ではありませんでした。彼曰く、“スピノザの神”(汎神論)です。彼は極めて合理的な思考の持ち主でしたので、これは科学的世界観と矛盾しない範囲での素直な感情の吐露だったのでしょう。
今回の“愛”についても同様と考えられます。“愛”という表現は、宗教的な意味合いというよりは、最高の調和をもたらす宇宙的な力という風に捉えられるでしょう。万物にあまねく浸透しているという意味で、究極的には、“愛”と“神”は一致することになります。
さて、この世界の調和のはたらきは、目に見えるものだけにはたらくわけではありません。科学の歴史が繰り返し示してきた通り、見えないものを含めてはたらくのみならず(ex. 電磁場、重力、ダークマター)、時間と空間を超えてはたらきます(ex. 相対性理論、量子力学)。これらの法則は極めて普遍的なので、森羅万象に及びます。だから、私たちが一見、破壊や死と捉える現象でさえも、その大いなるはたらきの中では再び合流し、調和するようになるといえるのです。
2.“愛”による救済と喜び
豊かな感性をもった先人たちが、その大いなるはたらきを感じ取り、「まるで魂が救済されたように感じた」と表現したのもそのためでしょう。そして、彼らは「自分が今、この世にあることの“真の喜び”を知った」と続けます。それは次のようなメッセージに聞こえてきます。「私たちは、例え死んだとしても、目に見えない世界において、大いなるはたらきにより再生される。そうであれば、死ぬからといって嘆くことはない。それよりも、生きていることを素直に喜べばいいではないか!」
ニュートンが万有引力に神の摂理を感じ、アインシュタイン博士が一匹の虫に神の偉大さを感じ、「世界の壮大な構造をみるだけで十分」と語ったことは有名です。このような感嘆は、世界の本質を永遠不滅と捉え、私たちをその一部と捉える非創造物としての立場から発せられたものなのでしょう。
だから、彼らは、人間の本質は決して物質としての体に限定されるものではなく、より大きな存在の一部をなしていると考えました。だから、アインシュタイン博士は自分の死を重大視せず、より大きな生命の営みに関心を示したのです。これは量子論的な視座に一致します。そのような意味で、この世での自分の存在を“仮の姿”だと捉えたのです。不思議なことに、歴史的著名人の多くが、このような感覚をもっていました。
古くは、プラトンのイデア論、ショーペンハウエルの「意志と表象としての世界」、聖徳太子の「世間虚仮唯仏是真」、敦盛の「夢幻の如くなり」など。
近年では、手塚治虫氏が「生命はより宇宙的なもので、私たちの命は、その宇宙的生命が少し滞在したものに過ぎない」と語り、瀬戸内寂聴さんは「体が死んで焼かれても、魂は生き続ける」と語りました。ノーベル物理学賞を受賞したロジャー・ペンローズ博士は、量子脳理論のなかで、人間の意識は量子的な実体として死後も存在し続けると語っています。また、『死は存在しない』(田坂広志著、2022年)でも意識の不滅性について述べられています。
少しニュアンスは異なるかもしれませんが、近年提唱されたシミュレーション仮説も同じことかもしれません。世界の大富豪イーロン・マスク氏は「私たちは仮想現実を生きている」と断言しています。
以上のような視点に立てば、“死”はもはや怖いものではなくなります。そして不思議と、生きる辛さも何だか軽く感じてきます。まるで、命の重責から解放されたような感覚です。
そのような心の境涯では、もはや、生きる絶望や死の恐怖に怯える日々でなく、むしろ、この命をどう生きるかに気持ちが向かうようになります。それなら、“命”とはどのようなものなのでしょう?
科学と哲学の叡智は、“命”をこの世界”の分身と捉え、“この世界”と同じ特性が“命”にもあると捉えます。例えば、ギリシアの哲学者ゼノンは、世界の本質である理性が人間にも宿っているとし、それを種子的理性と名付けました。東洋哲学では、例えば「心則理」であるとか「人には仏性が宿っている」などと表現します。
量子論では世界を一体と捉え、人間を世界から分離した存在でなく、世界に内在した存在として捉えますが、今や、多くの最先端研究分野でそのような捉え方が主流となりつつあります。例えば、エコシステムや地球のガイア論もそうです。そういえば、SDGs(持続可能な開発目標)の発想もそこにあるのではないでしょうか?
そして、このような一体世界は、自然発生的に湧いて出たものではないという主張につながります。いわゆる超越的存在が宇宙を創造したという“有神論的世界観”です。よくビッグバン宇宙論を引き合いに出して、「宇宙は偶然に生まれた」という人がいますが、そうではありません。これは宇宙の誕生を火の玉から発生したというモデルですが、火の玉がどのように発生したかについては何も語っていません。何か特別な力がはたらいた結果、生じたということを排除しているわけではないのです。
無から突然、量子揺らぎによって宇宙が誕生したというモデル(A.Vilenkin)は確かにあります。また、あの天才物理学者ホーキングの言葉「宇宙の創造に神のような第一原理的存在は不要」を引き合いに出すかもしれません。
でも、歴史上、多くの科学者はそうは考えませんでした。その考え方では、この世界を埋め尽くす調和や、アインシュタイン博士の語った“世界の壮大な構造”、更には、その本質をなす“愛”のはたらきを説明できないからです。だから、現代でも科学者のなかでは有神論的世界観を持つ人が圧倒的に多いのです。
ちなみに、私自身も有神論的世界観を支持しています。しかし、私には先人のような天才的インスピレーションはありません。ただ、現代科学では「神の存在を証明できていませんが、否定もしていない」という事実と、科学的天才たちの言葉、および、先人たちの揺るぎない信念を信頼しているだけです。
それに、神が存在しないとすれば、身を涸らす修行も、未来に願いを届ける即身仏も無意味になってしまいます。これでは絶望しかないといわざるを得ません。しかし、神が存在するとなれば、すべての見え方が変わってきます。すべてが神につながっていると思えば、どんな苦しみにも我慢できそうです。まさに最強の自分になれる気がします。
少し脱線しましたが、万物一切が、そのような“愛”のはたらきが引き起こす因縁の集まりであるとしたら、もはや、“私”に固有の本質を想定する必要は感じられなくなります。近年の情報科学の飛躍的な発展、特に、AI研究の進展から生じた、「私たちが“私”と思っている自分は、実は、生まれてからの経験によって形成された」という見解にがっかりすることはありません。むしろ、私たちの存在が“愛”に包まれたものであることに気付き、安心するのではないでしょうか。ちなみに、汎神論を唱えたスピノザは、この“愛”に「溺れている」と表現されるほどの至福を感じたといわれます。
3.”愛”に立脚した新しい生き方
そんな自分をよりよく生きるやり方についても、先人たちは語っています。それは、「私たちの姿や形に自分の本質はない」として囚われないということです。姿や形といった私たちの“体”は物質的なものなので、破壊と消滅をまぬがれません。つまり、老化や病は防げないということです。だから、体に執着しても、その期待は必ず裏切られます。それよりも人間らしい普遍的な思いを“徳”と表現して尊び、肉体的、あるいは物質的な欲に固執する自我の殻を破る重要性を説きました。
ギリシア哲学における四元徳(知恵、勇気、節制、正義)、西洋哲学における三元徳(信仰、希望、愛)、古代中国の四端説(惻隠、恥悪、辞譲、是非)などです。
これらの徳は目に見えません。しかし、だからといって存在しないということにはなりません。科学的に表現すれば、ポテンシャルが見えないからといって存在しないことにはならないのと同様です。徳は、確かに私たちに影響を与える力を持っています。アインシュタイン博士は、これら徳を含めた大元にある宇宙唯一のエネルギーを“愛”としたのです。
世界を広く見渡す力がつけば、誰でもきっと、世界を動かす“愛の相関”に気付くに違いありません。ひとたびそれに気付けば、一見、破壊や消滅に思われる事象も、遠い相関をたどればその限りではないと気付きます。その大局的視座が安定すれば、遂には、一切に破壊を見ることのない境地である“心の平静”が得られます。そして、全ての営みに意義を見出し、納得のいく人生が送れるようになります。そのようにして死をも克服した人たちを、先人たちは聖人や聖者と言いました。
これは決して簡単なことではありません。アインシュタイン博士が指摘する通り、誤解や偏見が妨げになるかもしれません。しかし、世界の情報が整理され、学問が分野を超えて発展していけば、いつかは誰もが容易にアクセスできる知恵になるにちがいありません。
そうなれば、破壊的現象に心が乱されることはなくなります。生きる無意味さに空しくなることもなくなります。迷いの人生に徒に消耗することもなくなります。そして、死の恐怖に怯えることもなくなります。
これはとても素晴らしい視点で、人間の多くの根源的問題に対して万能の視座を与えてくれます。一例として、ここでは、死の捉え方についてみてまいりましょう。
私たちは元々、この世界には存在していませんでした。存在していなかったものが、存在することがあるのでしょうか?科学的には、存在していなかったものが現れたり、存在していたものが消えることはありません。エネルギー保存の法則に反するからです。まるで相対性理論の「質量とエネルギーの等価」のように、存在の形態が変わるだけです。
そうであるなら、存在の形態が変わっただけと考えてみてはいかがでしょうか?つまり、死とは、有形の体から無形の存在への変容である、と。では、どこへいったのでしょう?生まれる前と同じ状態、それは最も根源的な状態です。アインシュタイン博士によれば、それは根源的である故に“愛”であり、“神”と一致する状態です。つまり、私たちは、死によって、この世界を創造した“神”のもとへ還り、再び調和を取り戻すということです。
死の変容は苦しいかもしれません。でも、私たちが生まれたときも同じだったはずです。そこさえ潜り抜ければ、その先には再び“調和”が待っていて、きっと、神の”愛”を存分に受けることでしょう。神の世界は永遠なのですから、それは“永遠の命”といえるかもしれません。地球が滅び、太陽が滅び、宇宙が滅んでも、永遠に神と共にあり続けるでしょう。
また、親、兄弟姉妹、家族の誰もが世界と一体です。だから、そこにいるのは“私”一人ではありません。親、兄弟姉妹、家族みな共にあり続けます。こんな素晴らしい未来が待っていると思えば、この世で多少の不便があったとしても我慢できる気がしてきます。このように、欲を求めることなく、慎ましいあり方を貫く生き方が、“愛”に立脚した生き方です。
4.死を知る本当の意味
このように、死を洞察すれば、この世で生きる死別や悲愁のつらさが軽くなります。ある意味、人生で最もつらい出来事である“死”を克服するので、絶対安定の精神が得られるといってよいかもしれません。同時に、生きる意味を知り、真の喜びを得ることもできます。そして、真の喜びを重ねれば、一度限りの人生を悔いなく過ごせるに違いありません。これが死に向き合う真の意味です。
本講座のなかでは、世界観を構築する過程で、その本質である“愛”の科学的なはたらきについて様々な視点から学びます。それにより、世界への信頼を回復させ、“心の安全基地”を形成します。そのプロセスが適切に行われれば、たとえ人生や自分の境遇が辛いものであっても、「愛しているよ」「ありがとう」と言えるようになります。
本講座は、人を信じられなくなった人が人生への信頼を回復したい、或いは、働くためだけに生きているような惨めな気持ちを払拭したい、さらには「なぜあの人はいつも幸せでいられるのだろう?」と羨ましがられる存在になってみたいという方に、ご興味を持っていただけましたら幸いです。一度、『あなたの幸せ強度診断テスト』をトライして、本講座で期待される効果をご確認くださいませ。
思伝門下塾 池之内 亨
2025年02月28日 13:39